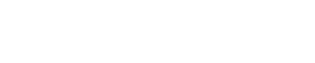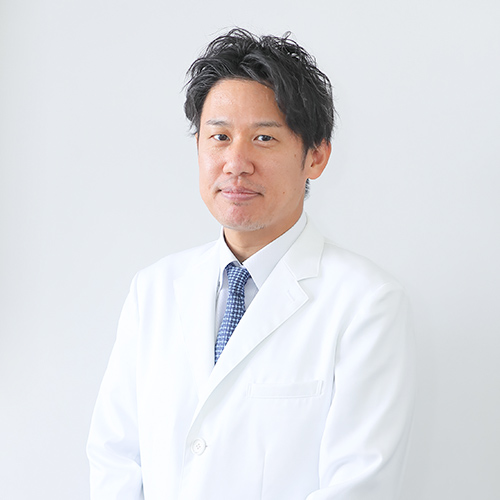歯の神経まで達したむし歯(C3)など、むし歯が重度に進行した場合は、歯の神経を除去する抜髄(ばつずい)を行います。
抜髄とセットで行われるのが、歯の根っこ(根管)の内部を綺麗にする「根管治療」です。
根管治療には、根管内部の細菌感染を抑え、歯(歯根)を残す役割があります。
歯を残す役割がある根管治療ですが、根管治療後は歯がもろくなってしまうため、歯根破折(しこんはせつ)などのトラブルが起きやすくなります。
目次
■根管治療後、歯がもろくなる理由
◎根管治療によって歯髄を取り除くと、歯に栄養が届かなくなり、歯がもろくなります
歯の神経を除去する処置、抜髄。
抜髄では、歯ぐきから上の歯の中央部分(歯髄腔)にある、神経や血管が集まった
「歯髄(しずい)」を除去します。
抜髄とセットで行う根管治療では、歯の根っこである根管内部に通う歯髄(歯根部の歯髄)を除去します(=歯根部の抜髄)。
[歯の中にある「歯髄」を構成する主な器官]
-
歯の神経(根管部分の歯の神経)
-
血管
-
リンパ管
歯髄は歯の神経が通うと共に、顎の骨から伸びる血管(血液)を通じて歯に栄養を送り届ける重要な器官です。
根管治療によって歯髄を取り除くと、血管がなくなるため歯に栄養が送られなくなり、歯がもろくなります。
例えるなら、根管治療後の歯は、水や二酸化炭素(木の栄養)が送られなくなり、枯れやすくなった木のようなイメージです。
■根管治療後は歯根破折が起きやすくなります
◎日本人の歯を失う原因の第3位は歯根が割れたり折れる「歯根破折」
歯根破折とは、歯根が割れたり折れることを指します。
歯髄が残っている歯と比べて、根管治療を受けて歯髄を除去した歯は歯根破折が起きやすいです。
特に、中高年の方に歯根破折が多く見られます。若い頃、または、数年~10年以上前などに根管治療で歯の神経を取り除いた歯がもろくなり、長年のダメージの蓄積によって歯根破折が起きるケースが少なくありません。
事実、日本人の歯を失う原因の第3位は歯根破折です。歯を失ったケースの2割弱において、歯根破折が原因で歯を喪失しています(※)。
(※)公益財団法人8020推進財団
「第2回 永久歯の抜歯原因調査」(2018)
より引用。
◎歯根破折は歯を残せないケースが多いです
歯根の割れ方や受診のタイミング(できるだけ速やかな受診が望まれます)によっては、接着剤を用いて歯根をくっつけ、歯を残せることも。
ただし、歯根破折で歯を残せるケースはあまりありません。歯根破折に対しては、多くの場合、抜歯処置を行い、抜いた部分の歯をインプラントなどの補綴治療で補う形になります。
■根管治療後に起きることがある疾患
治療時の刺激や根管内部の細菌の取り残しなどの原因により、根管治療後は以下のような疾患が起きる可能性があります。
①根尖性歯周炎
根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)とは、歯の根の先(根尖)に炎症が起きる疾患です
[根尖性歯周炎の主な原因]
-
むし歯の進行による根管内部の細菌感染
-
根管治療時に根管に受けた刺激
-
根管治療における根管内部の細菌の取り残し
根尖性歯周炎は痛みを感じないケースもあります。ただし、根尖性歯周炎が重度に進行した場合は歯ぐきや骨膜が炎症を起こし、眠れないほど強く痛むことも。
進行した根尖性歯周炎では、歯ぐきの中に膿の袋「フィステル(サイナストラクト)」ができるケースも珍しくありません。
フィステルができた場合は、歯ぐきの切開による排膿処置(膿を出す処置)や歯根端切除など、外科的な処置・手術が必要になることもあります。
②歯根嚢胞
歯根嚢胞(しこんのうほう)とは、歯の根の先に袋状の嚢胞(のうほう:組織から浸み出た滲出液が溜まった袋)ができる疾患です。
[歯根嚢胞の主な原因]
-
むし歯の進行による根管内部の細菌感染
-
根管治療時に根管に受けた刺激
-
根尖性歯周炎の進行
-
根管治療における根管内部の細菌の取り残し
-
歯根破折
歯根嚢胞を発症すると、食べ物を噛んだときに歯の根元や歯ぐきにズーンとした痛み(圧痛)を感じることがあります。圧痛に加え、歯根嚢胞では歯根の先端にできた袋が大きくなって顎の骨(歯槽骨)が溶け、歯がグラグラになるケースも。
歯根嚢胞ができた場合は、嚢胞を取り除くために外科的な手術が必要になることがあります。
【早期受診、および、毎日のセルフケア&歯科医院で受ける定期メンテナンスが重要です】
根管治療は、主に進行した重度のむし歯治療で行われます。根管治療を行わずに済むようにするためには、むし歯が進行する前に、ちょっとでも歯にしみや痛みを感じたら、速やかに歯科医院を受診することが大切です。
速やかな歯科医院の受診に加え、歯の健康を守るには、毎日のセルフケア(歯みがき+歯間清掃)&歯科医院で受ける定期メンテナンスが重要になります。
当院の根管治療についてはこちら。